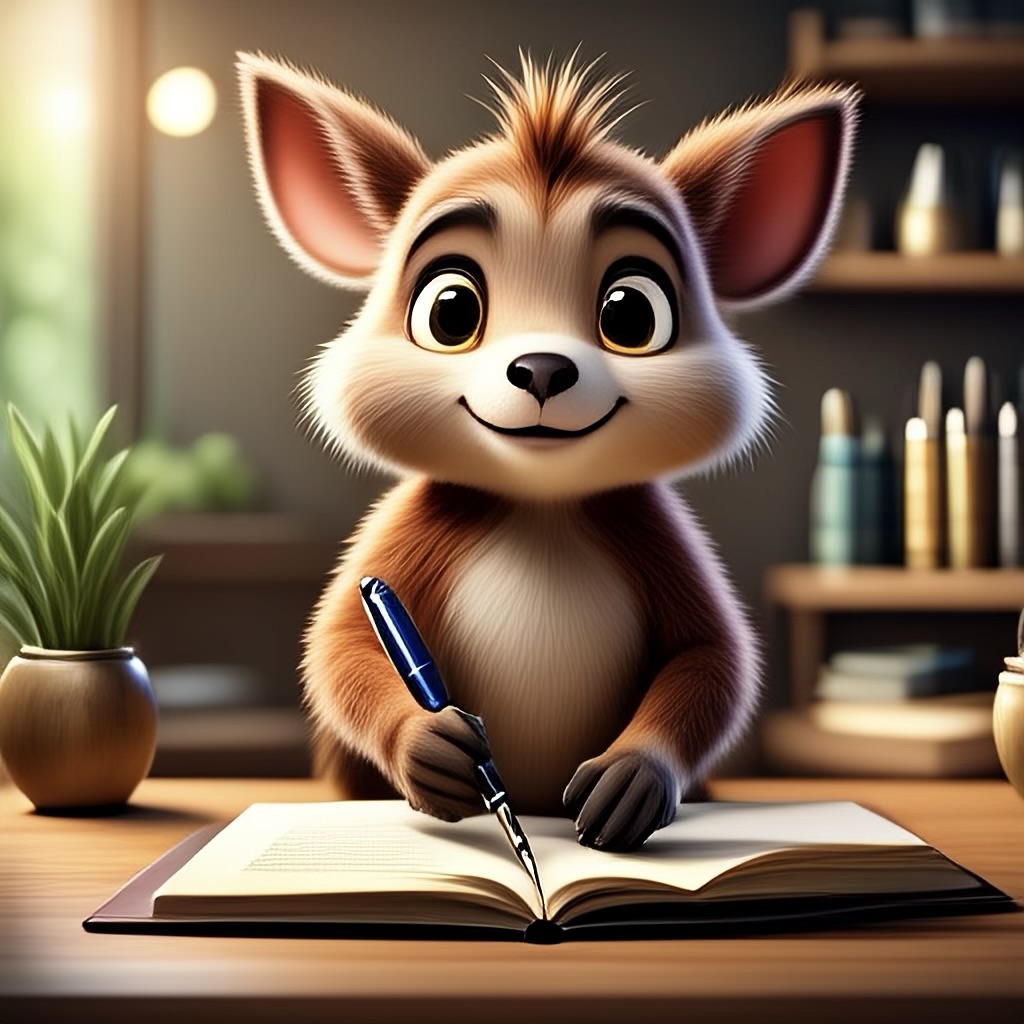
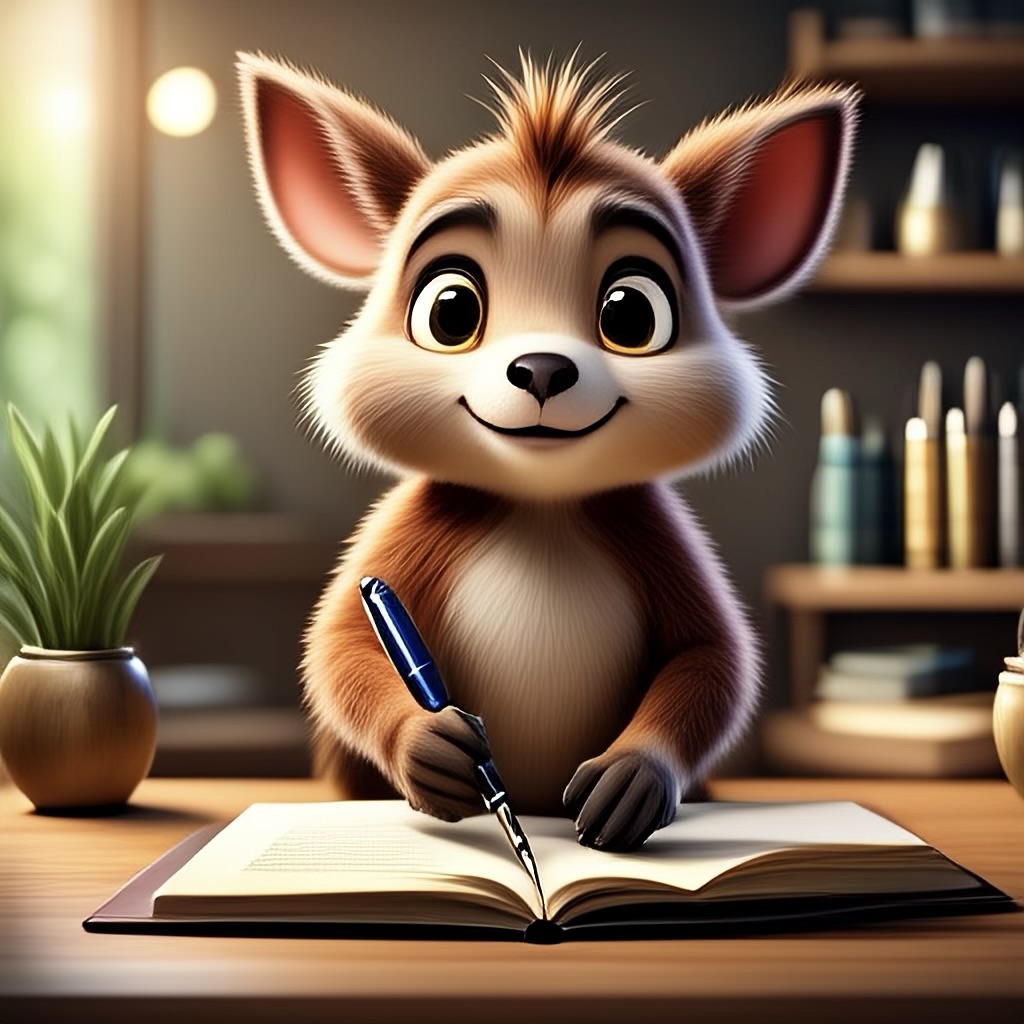

少量多品種、付加価値商材…その前に…

コンサル活用について

コンサルティングの価値は外部だからこそ組織の論理に問わられない発想や行動をサウンドバックになりながら促すという点もありますし、
実際の取り組みの中身として、会社の利益につながるような実益としての価値は当然あって然るべきです
そして、もう少し加えて言えば、
持続性と再現性を価値に加えたいと考えています
持続性とは、生み出す価値、実益が一過性ものではなく、持続性するということ
再現性は、生み出された当該価値や実益ではなく、別の課題や困難に直面しても、考え方やプロセスを以て、新たな価値、実益を生み出すという類似の再現可能性を高めること
もちろん、持続性も再現性も簡単ではなく、
一過性でも改善すればそれはそれで、価値はあると思います
しかし、問題解決者の姿勢としては、持続性と再現性の価値も作り込むという姿勢でいたいです
コンサルは内情を深く知る立場にありますので、情報流通や物品流通など、ブローカー的な活動が可能です
しかし、それをやりだすと問題解決より安易な稼ぎ方に身が慣れると、主眼がそちらに移り変わってきます
これは、自戒であるとともに、人間の脆弱性と思いますし、誰にでも起きることと思います
ですから、あえて難しい姿勢を貫くことが、自身の問題解決者としての持続性と再現性につながると考えます
問題の構造の解き明かしと、その根源を断つことで実現可能です
よくあるのが、問題をヒアリングして、並べて、優先順位を決めて…
という積み上げ式の取り組みを見かけますが、これだと、
リストアップされたものが終わったらお終いとなること
そもそも対処療法的であり、一つ潰してもまた別の課題が生み出されれること
一つ一つ潰していると改善活動自体の生産性が低いこと
これらが問題となります
ヒアリングや現場を見ること、外の世界を見ることで感じる違和感や顕在化した問題をリストアップするのは良いので、
それを個々に潰し込みにいかず、
まずは、それら問題がなぜ起きるのか?を一呼吸置いてじっくり考えるべきです
因果関係の線を引くのも良いと思います
その上で、要は何をすることが大切なのか?何をしてなかったことが問題なのか?
問題解決のコンセプトを考えて見てください
コンセプトから、活動のテーマを決めて、テーマから具体的な施策を考えて見てください
この流れは、個々の課題から、コンセプトやテーマという抽象的な次元に一つあげて、
そこから改めて具体に次元を落とす作業です
一度抽象度をあげてから、具体策を考えると、今出てきている施策以外のアイディアが生まれます
あくまで大切なのは、改善のコンセプトやテーマの実現であり、施策はそこに至る手段です
ですので、コンセプトを実現できたのか?テーマが実現できたのか?を問うことが大切で、個々の施策ができたのか?は管理上は重要ですが、改善活動においては一過性の問いにすぎません
これらを進めていけば、持続的な活動となり、持続的な価値、実益に繋がりやすくなります
再現性の観点は、上記の一連の取り組みを、一定のフレームワークやツールを利用することでもある程度は再現可能ですが、
やはり大切なのは、そういったテクニカルな話ではなく、
経営に対する考え方、組織に対する考え方、改善活動に向き合う考え方、などなど、
どう考えれば突破口が見えるのか?見えてくるのか?という思考にあると思います
組織で問題解決を行うには、思い立ったらすぐに行動は大切な局面もありますが、組織を動かすにもいろいろなコストがかかりますので、
ある程度は見定めてから組織を動かす方が、改善活動疲れや改革疲れを避けられます
しっかりと考えること、組織の動かし方、これらをしっかりと、クライアントと共有しあい、ともに問題解決していくという、共創的なプロセスこそが再現性を高めると考えています
ただし、問題解決者は、共創的なプロセスという言葉で、議論を受け身で対応すれば良いという安易な考え方に陥るのは絶対にダメです
共創的にプロセスに至る初動はコンサルがしっかりと考え抜き、仮説を持ち、しっかりと議論をリードしながらも、新たな情報や考え方の更新により、仮説を柔軟に更新しながら、理想と現実のバランスの中で論点を進化させ、実現させるということです
なお、コンサルは資料作りが多くなりますし、昨今資料づくりにそこまで比重をかけないという取り組み方はありますが、
この再現性という意味では、思考のプロセスがわかる資料は非常に有益です
未来にも使われるかもしれない、誰かが参考にするかもしれない資料については、まとめ方含めて、残していくのも大切なことと考えます
持続性と再現性は非常に難易度が高いと思いますし、私など諸先輩方には遠く及ばないところではありますが、常に肝に銘じて取り組みたいと思います